充実した学び

清泉では、恵まれた自然環境や多方面で活躍する卒業生の協力により、ここでしか触れることのできない多様な学びが実現しています。また、チャレンジ精神豊かな生徒たちによる自主的な活動や、教員と学習メンターのサポートにより、充実した学習環境が整っています。
特色ある学び
空手集団演武(体育)
中1・中2の体育では、武道の単元で空手を学びます。基本の形からはじめ、中2の最後は組手を練習します。体の使い方だけでなく、礼を大切にする精神も身につけます。


空手指導者 諸岡奈央(卒業生)
全日本学生選手権4連覇、2006年アジア競技大会優勝、2008年全日本空手道選手権優勝。東京五輪の空手解説者も務めた、本校卒業生が指導しています。
タンポポ分布調査(理科)
中1は、入学してすぐに野外調査を実施。学校の敷地内で在来種と外来種のタンポポの分布調査を行い、採取した花を解剖して特徴を理解します。

玉縄城フィールドワーク(社会)
清泉は、戦国時代の城である玉縄城の跡地に位置しています。中1・中2では、城のあった地域の地形の特徴と北条氏をめぐる歴史を実地によって学びます。

修学旅行(高大連携)
高2の修学旅行は、長崎・沖縄・台湾の3コースから選択します。修学旅行前の事前学習として、清泉女子大学の教授によるコース別のハイレベルな講義を受講します。

学習サポート
学びを促すクラス編成と学習支援
習熟度別授業+少人数制
学力の素地となる国語(古典)・数学・英語は、それぞれの生徒に寄り添った習熟度別授業や少人数制授業を導入しています。

「未来手帳」で習慣づけるPDCAサイクル
低学年のうちからPDCAサイクルを重視し、清泉オリジナル手帳を利用して、宿題や提出物だけでなく試験や検定等の目標・計画・振り返りまでを一元管理しています。
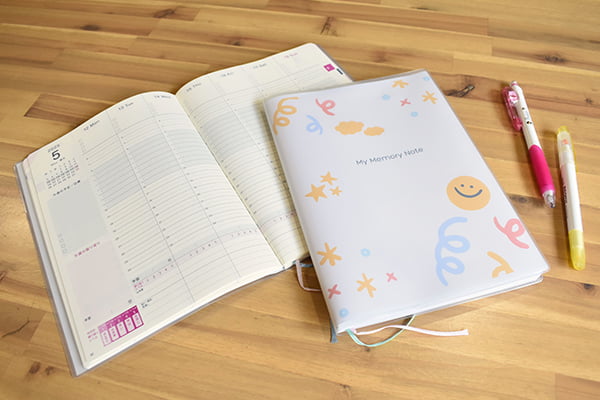
定期試験補習
定期試験の成績が基準に達しなかった中学生は、平日開講される無料補習の対象となります。分からない部分を無くしてから次の単元に進めるよう支援しています。
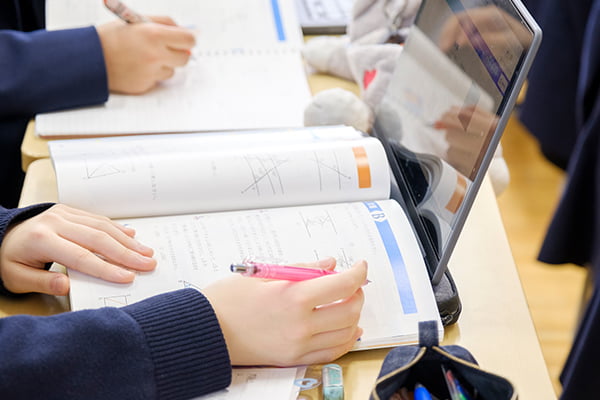
チューターPlusによるサポート
自習室の活用
学習メンターが常駐する自習室の利用が可能です。退室(帰宅)時間が保護者に通知される安心機能もあります。
平日[中学生]18:00まで [高校生]18:30まで
土曜・長期休暇中 16:00まで

多彩な特別プログラム
英検合格や定期試験の成績向上を目指す講座、模試の解き直しを行う企画、長期休暇中の宿題を進める企画など、目的に特化したプログラムが定期的に開かれています。








